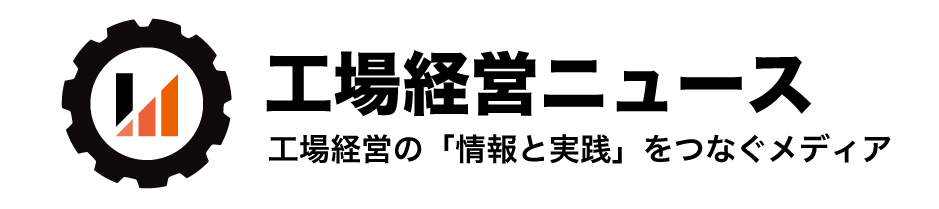2025年3月24日、埼玉県産業振興公社主催「デジタルものづくり改善研究会 令和6年度成果共有会」が開催された。同公社では、2024年度に3回「Power Platform研修」を実施しており、研修を受講した埼玉県内の2社が、Power Platformを活用して開発したアプリの成果を共有する場となった。
冒頭、主催する埼玉県産業振興公社の新産業振興部の松本健太郎氏からは、「今日ご参加の2社から、アプリを開発する技術者視点と経営者の視点から話題提供をいただきつつ、フリーなディスカッションを通じて情報交換できる場にしていきたい」との主旨説明があった。
▼Power Platform研修の概要はこちら
タイムテーブル
1.主催者挨拶
2.ノーコードツール活用事例紹介
①サーマル化工株式会社 「熱処理工程の見える化アプリによる管理工数の削減」
②セキネシール工業株式会社 「製造現場の手書き日報入力のアプリ化」
3.開発者フリーディスカッション
〜開発技術、適用・運用ノウハウ、相互アドバイス〜
4.DX活用フリーディスカッション
〜経営課題解決につなげるDX活用の考え方〜
5.まとめ

Power Platformで開発したアプリの事例共有
今回の報告会では、サーマル化工株式会社とセキネシール工業株式会社の2社による報告が行われた。両社はともに、Power Platformに触れてから1年程度あり、今回開発された方はIT関連の経験も少ない。研修で学び、調べながらアプリ開発に挑戦してきた。
サーマル化工株式会社からは、「工程管理アプリ」の開発事例が紹介された。業務工程の進捗を可視化し、作業全体の進捗状況を可視化することでトラブル発生時の早期発見につなげ、納期遅れを防ぐことを目指して開発された。開発中の苦労はもちろんあるが、実際に開発したアプリを利用する人にフィードバックを求めると「想定外の意見」がくることもあったそう。引き続き利用する現場の社員の意見を聞きながら、アプリのリリースに向けて取り組んでいくそうだ。
また、報告した同社の社員は、「Microsoftの製品を使ってここまで自由にアプリを作れるとは思わなかった。興味を持てたので、今後も知識を増やしていきたいと思う」と話していた。

一方、セキネシール工業株式会社では、「日報アプリ」を作成した。これまでは、手書きで書いた作業日報を担当者が生産管理システムに半日がかりで登録していた。日報をデジタル化することで、作業工数を減らすことを目指している。
報告に対して会場からは、「作り込まれたアプリであり、管理者側のメリットは大きいだろう。しかし、作業者にとっては記入するところが非常に多く、導入に対して抵抗はなかったか」という質問があった。これに対しては、「弊社の日報は、もともと人主体の日報であり、細かい記載を求めていた。そのため、これまで手書きで記載してきた内容をデジタル化しただけであり、抵抗はなかった。」そうだ。

開発事例報告からは、2社がともに、自社の課題を解決するための方法としてPower Platformを活用していることが窺えた。既存のサービスを利用することで解決できる可能性もあるが、自社にとってより最適なものを自分たちでつくり、改善しながら業務を改善する「理想的なDX」の取り組みではないだろうか。
企業の垣根を超えたフリーディスカッション
フリーディスカッションでは、サーマル化工株式会社常務取締役の齋藤氏が、同社がDXに取り組み意義を経営の視点から紹介した。
サーマル化工株式会社では、埼玉県産業振興公社のサポートを活用しながら自社分析を徹底し、現在は営業力をデジタル活用で向上させる取り組みが進んでいる。自社分析を通じて自社の特徴や強みを再認識し、新規顧客の獲得で注力する業種を絞り込んだ。そのうえで、潜在顧客へ効率的にアプローチするための手段として、デジタルの活用を進めている。
自社の課題を特定したうえで、その解決策にデジタルを活用するかどうかは「経営判断」だ。ディスカッションでは、セキネシール工業株式会社の関根社長を中心に、業界の特殊性を踏まえた営業コストの面から質疑が行われた。

【編集部の視点】学びの深化は「観察」から
報告会に参加した私が注目したのは、「Power Platformの学びやすさと習得の難しさ」だ。開発事例報告の際にも質疑応答で話題に上がっていたが、これまでIT経験の少なかった人でも、研修を通じてある程度学習するとすぐにアプリを開発できるようになった。これは、他のMicrosoftサービスと利用方法が似ていることや、通常のアプリ開発(フルスクラッチ開発)と比較しても、開発行程がわかりやすい構造になっていることが一因だろう。
一方で、報告者からは「学んだ開発知識を自分のものにできていない」という発言も見られた。初めて開発する人でも調べながら開発することはできるが、実装したい機能に応じて知識に応用を効かせることや、知識から開発方針を発想することに難しさがあるようだ。これらの課題には、どのようなものでもある程度の「慣れ」や「経験」は必要である。学んだ知識を自分の力に変えるためには、自らの開発経験だけでなく、他者の様々な開発事例から機能の構造や仕組みを観察することが大切だ。