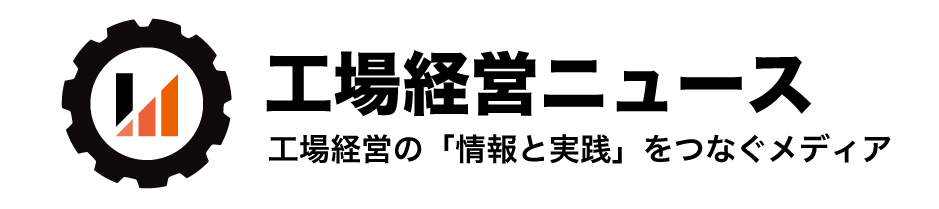来ハトメ工業株式会社は、1946年に東京都荒川区で「來商店」として創業し、現在は埼玉県八潮市に本社を構える金属プレス加工の専門企業です。主力製品であるアルミ電解コンデンサ用アルミケースは、外径φ3mmから10.2mmまでのサイズを毎月約2億個製造・出荷しています。また、2002年からはアルミ製リベットの製品開発にも着手し、現在では4種類のリベットを取り扱い、十数年にわたり品質クレームゼロの実績を誇ります。
環境への取り組みにも積極的で、全工程における化学物質対策や脱炭素化を推進し、年間の二酸化炭素排出量を10t以下に抑えるなど、環境経営の分野で高い評価を得ています。さらに、2017年からはSDGs(持続可能な開発目標)にも取り組み、持続可能な社会の実現に貢献しています。
今回は環境管理責任者として、来ハトメ工業の環境への取り組みを推進された石原様にお話を伺いました。
石原 隆雅 / Takanari Ishihara
5年半の商社勤務を経て2005年10月来ハトメ工業㈱入社。2010年6月からEA21環境管理責任者に就任。以来、従業員を成長へと導く環境活動を一貫して推進。短期間で環境ドシロウト集団を環境先進企業へと進化させることに成功する。
現在までに過去6度「環境コミュニケーション大賞」(第15、16、18~21回、第16回、第20回は環境大臣賞))の受賞をはじめ、「環境・人づくり企業大賞」(第1、2回、第1回は環境大臣賞)、「彩の国埼玉環境大賞」(第17回、優秀賞)と、環境関連各賞を受賞。
2020年12月には、エコアクション21審査員試験に合格。現在、企業の環境管理責任者とエコアクション21審査員という前代未聞の二刀流に絶賛挑戦中!

GXに取り組み始めたきっかけとエコアクション21の採用
ーーGXに取り組むことになった背景を教えてください。
もともとは、お客様からの要請でした。2008年に『環境認証を取得せよ』と言われたのが始まりです。それまで環境対策に関しては全く意識していませんでしたね。そこで、まずはISO14001の取得を目指しました。しかし、リーマンショックが起こり、それどころではなくなり、半年ほど手をつけられていませんでした。
ーーそれでも最終的に環境認証を取得されたのはなぜですか?
得意先から継続して要請がありました。当時の社長は『そんな金のかかることはできない』と言いましたが、ISOは確かにコストがかかります。しかし、お客様から『エコアクション21という選択肢がある』と聞きました。環境省の制度で、ISOとほぼ同じ要求事項がありながらも、分かりやすく書かれていて中小企業向けだったんです。
そこで、県が主催する勉強会に参加し、取り組みを開始しました。結果、2010年9月に認証を取得しました。しかし、この時点では『お客様に取得しましたよ』と言うためだけのもので、GXや脱炭素の意識はほぼゼロでした。
環境問題への意識の変化と節電の取り組み
ーーGXや脱炭素に本格的に取り組み始めたのはいつ頃ですか?
2011年の東日本大震災が大きな転機でした。計画停電が実施され、電気の使用量が毎日発表されるようになったことで、電力に対する意識が変わりました。それまで『二酸化炭素と電気の関係』を意識していませんでしたが、工場内の水銀灯をLEDに変えることでデマンドを下げられるのではないかと考え、徐々に節電の取り組みを始めました。
ーー取り組みを進めるうちに、どのような成果が生まれましたか?
エコアクション21の環境活動レポートを毎年作成し、全国規模の表彰制度(環境コミュニケーション大賞)に挑戦しました。初年度は落選でしたが、翌年は奨励賞、さらにその翌年には大賞を受賞しました。こうした活動を通じて『環境に取り組むことで企業価値が高まる』と実感しましたね。
さらに、工場の洗浄設備を重油から電気式に変えたことで、二酸化炭素排出量が46%削減されました。これは、日本政府の2030年目標と同じ削減率で、結果的にGXが進んでいたことになります。
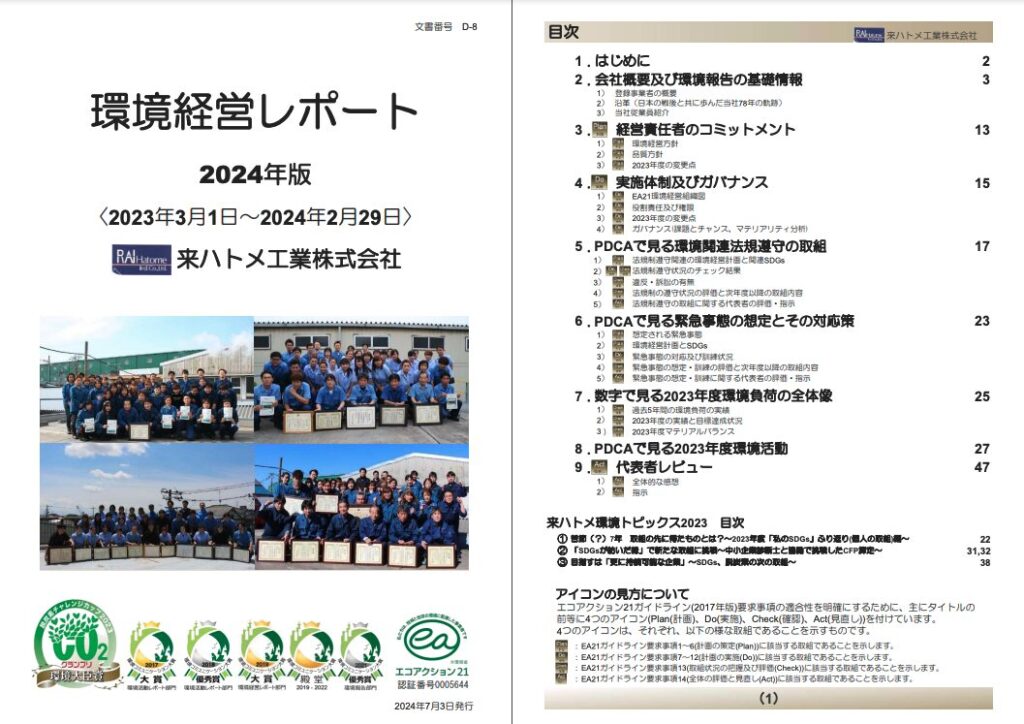
グリーン電力への挑戦と環境経営の進化
ーーグリーン電力の活用はどのように進められたのですか?
環境に関する情報を集める中で、『グリーン電力』の存在を知りました。太陽光、風力、バイオマスなどの再生可能エネルギーを利用する電力会社があり、排出係数がゼロの電力です。それなら、グリーン電力に切り替えれば二酸化炭素排出量をゼロにできると考え、2017年11月から導入しました。
ーー周囲がグリーン電力に注目する前から先行されていたのですね。
そうですね。2016年には、東大の教授の講義で『2050年には50〜80%の排出削減が求められる』と聞きました。そこから『GXは間違いなく進む』と確信し、2017年には『2030年までに50%削減』という独自目標を設定しました。結果的に、この目標もほぼ達成しています。
環境経営に対する社内の反応と取り組みの広がり
ーー社内での取り組みの反応はいかがでしたか?
最初は誰も関心がありませんでしたね。環境認証の取得も、『言われたからやる』という程度でした。しかし、表彰を受けるなど、成果が目に見えると、社内の雰囲気も徐々に変わってきました。
私自身も責任者となり、環境活動の知識を深めるために勉強を重ねました。甲種危険物取扱者、公害防止管理者(大気・水質1種、騒音振動)などの資格を取得し、最終的にはエコアクション21の審査員資格も取りました。

ーー社員の巻き込みはどのように進めましたか?
環境活動を経営戦略に組み込み、現場の従業員にも役割を持たせました。例えば、現場での節電活動やデータ収集を担当してもらうことで、全員が関与できる仕組みを作りました。
中小企業がGXに取り組む意義と今後の展望
ーーGXに取り組む中小企業の意義について、どのようにお考えですか?
企業は環境問題に積極的に取り組むことで、社会的な評価を高めることができます。特に中小企業は、早く動けば注目されやすく、環境先進企業としてのポジションを確立できます。
実際に弊社も、環境コミュニケーション大賞などを受賞したことで、メディアや業界内で注目されるようになりました。GXへの取り組みは、単なるコストではなく、企業価値向上につながる投資だと考えています。
ーー今後の目標を教えてください。
すでに99%の排出削減を達成しており、次の目標は2035年のカーボンニュートラルです。これは、世界的な流れを見据えた長期目標です。
また、審査員の立場として、環境経営に取り組む企業を増やすための支援活動にも注力していきます。企業のGX推進をサポートし、持続可能な社会づくりに貢献できればと考えています。
最後に
今回は来ハトメ工業株式会社の石原様にお話を伺いました。環境認証の取得から、表彰を受けるまでの過程、そしてグリーン電力の活用まで、着実に進まれてきた姿勢が印象的でした。環境経営に取り組むことの目的や具体的な取り組みまで理解を深めることができるインタビューでした。